
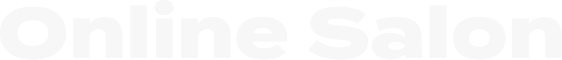
2025.06.26
皆さん、こんばんは!
今回は「姿勢」と「感情」の深い関係についてお話しします。
「姿勢と感情?え、何それ?」と思いますよね。
姿勢というと「肩こり」「腰痛」「猫背」といった「体の話」だと思われがちですが、実は姿勢は、心・感情・ストレス耐性・思考の質にまで影響するというのが最近の研究で分かってきています。
心理学や神経科学の分野ではすでに、「気分が落ち込むと姿勢が悪くなる」だけでなく、「姿勢が悪いと気分も沈む」という逆方向の影響もあることが確認されています。
たとえば、サンフランシスコ州立大学の実験では、
姿勢をわざと悪くした状態でネガティブな言葉を思い出してもらうと、感情がよりネガティブに傾く傾向が出ました。
一方で、背筋を伸ばしている状態では、同じ言葉に対して「気にならない」と感じる人が多くなったそうです。
つまり、
「ストレスがあるから姿勢が崩れる」のではなく、姿勢が崩れているからストレスに弱くなる、というケースも十分にあり得るということです。
① 横隔膜と呼吸の連動
猫背になると胸がつぶれ、横隔膜がうまく動かなくなります。
その結果、呼吸が浅く・早くなり、自律神経は交感神経優位(緊張・不安・焦り)に傾きます。
呼吸が浅い状態では、本人は「焦っている」と自覚していなくても、
脳と神経は常に“戦闘モード”に切り替わっており、心の余裕がなくなります。
② 姿勢センサーと脳の安心感
背骨周辺の筋肉や関節には、常に姿勢をモニタリングしている「固有受容器」と呼ばれるセンサーがあります。
これらは脳に「今の身体の状態は安定しているかどうか」という安全信号を常に送り続けています。
姿勢が崩れていると、このセンサーが「不安定」「警戒モード」と判断し、無意識に防御的・緊張的な状態を生み出してしまいます。
つまり、
姿勢とは単なる形ではなく、「脳に送る安心のスイッチ」なのです。
③ 姿勢とホルモンの変化
ハーバード大学の研究では、胸を開いて堂々と立つ「パワーポーズ」を2分間とるだけで、
テストステロン(自信・決断力)→ 20%上昇
コルチゾール(ストレスホルモン)→ 25%低下
という変化が観察されました。
反対に、背中を丸めて縮こまった姿勢をとると、自信が減り、不安を感じやすくなり、リスク回避的な判断をしやすくなる傾向が出たそうです。
これは気の持ちようではなく、ホルモンのレベルで証明されている現象です。
以下の「姿勢リセットルーティン」を、朝や気持ちが沈んだ時に行ってみてください。
【所要時間:1分】
①壁に背中をつけて立つ(かかと・お尻・肩・後頭部がつくように)
②壁に押しつけるのではなく、自然な位置で姿勢を整える
③ゆっくりと深呼吸を3回(吸う3秒、吐く6秒)
④胸を開き、首をやや前に出す
⑤壁から離れて、そのままの姿勢で1分歩く
これだけで呼吸が深まり、自律神経が整い、集中力もぐっと上がります。
▼イライラしているとき
▼やる気が出ないとき
▼本番前に緊張しているとき
▼気分がふわついているとき
そんな時こそ、無理に気持ちを変えようとするのではなく、まず「姿勢」を変えてみてください。
姿勢は見た目だけの問題ではなく、「今の自分をどう認識しているか」を脳に伝える、大事なメッセージです。
背筋を伸ばし、胸を開き、ゆっくり呼吸する。
それだけで脳は「大丈夫だ」と思い出します。
自分の感情がコントロールできないときこそ、
身体のかたちから、整えていきましょう。
どうでしたか?
皆さんはこれを読んで何を思ったでしょうか?
来週も楽しみにしていてくださいね!